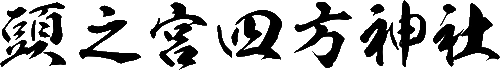皆様、伝統文化といいますとどのようなイメージがありますでしょうか。
日本の伝統文化といえば、皆様も親しみのあるものが沢山あると思います。お正月やお盆の行事、着物や和食や畳など昔からの衣食住、豊かな自然と季節とを背景とした風習、芸術作品…。現代では馴染みの薄くなったものも多いですが、こうして挙げると、昔からの伝統文化こそが日本を日本たらしめているといってよいと思います。
しかし「伝統文化」に対して、単に「伝統」と申し上げますと、何となく格調高いイメージや、堅苦しいイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。それは、多くの人が神社に対して抱くイメージとも重なるかと思います。

◆神社と「伝統」
神社の前に、神社を守っている神職が伝統を尊重し、伝統を次代へとつなぐ役割を持つことは、論を待たぬと思います。
当社を含め、全国の神社の多くを包括する神社本庁には「神社本庁憲章」という決まりが
あります。これは神社本庁ひいては神社・神職の在り方を規定した、実務というより規範の意味が強いいわば憲法のようなものですが、この前文には
神祇を崇め、祭祀を重んずるわが民族の伝統は、高天原に事始まり、国史を貫いて不易で
ある。
とあります。より分かりやすく表現すれば
八百万の神々を拝み、お祭りを大切にする日本人の伝統は、遠い昔である神様の時代に始まって、日本の歴史の中で変わることがありませんでした。ともいえるでしょう。
この「八百万の神々を拝み、お祭りを大切にする日本人の伝統」とは、神社にお参りしたり、お祭りに参加したりと、我々神職が、また皆様が普段なさっていることに他なりません。
つまり、ここで言われている「日本人の伝統」こそ「神道」であり、日本人が今も受け継いでいる伝統に他ならないのです。
であれば、神様がおわし、神職が守っていくべき神社は、日本人が神道を受け継ぐ為にふさわしい施設である必要があります。神社が「伝統」を体現しているのは、その意味では当然といえるでしょう。

◆伝統の意義
それでは、伝統の意義とは何でしょうか。伝統といいますと堅苦しいようですが、何故そこまでして守らなければいけないのでしょうか。
俗世間は時代と共に移ろいゆきます。人も変われば暮らしも変わるのです。神様のおわした時代とも、雅な平安時代とも、今は何もかもが違い、生活も比べ物にならないほど良くなりました。
しかし、その中において変わらないもの、守り伝えられてきたものの存在というのは、人々の心の故郷となります。
人の一生は波乱万丈で、不安なこと、悲しいことがたくさんあります。国も同じで、日本の長い歴史の中では苦しい時代がたくさんありました。今もそうでしょう。
しかし、少し立ち返れば我々には変わらないものがあるという安心感が、またそれを守りつないでゆこうという規範意識が、揺れ動く社会の中において人の心を安定させるのです。伝統とは、国の安定剤とでもいえましょう。まさしく、神様を大事にすれば良いことがあるという安心感が、悪いことをしようとすれば神様からバチが当たるという規範意識が、我が国を支えてきたのです。
勿論神様を拝んでいたとしても、これまでの歴史で困難は多くございましたが、もし日本人が神様を軽んじていたら、その困難はもっと大きいものであったでしょう。
同じように皆様の中でも、神様やご先祖様が見ているぞ、と心の奥底で思っていなかったら、ほんの少し悪いことをしてしまっていたかもしれない、という方はおられるのではないでしょうか。
伝統こそが社会を安定させるのです。そして、皆様が神社にお参りなさることひとつひとつが、私達のみならず次代の子孫たちも伝統の恩恵を受けられるように、神道という伝統を守りつないでゆく尊い行いなのです。
我々神職も、神社が神様のおわす場、また日本の「伝統」を実践する場として相応しい所であり続けられるよう、日夜努力しております。