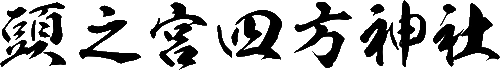今日は、どうすれば上手に人とコミュニケーションが取れるだろう?という疑問について、「聞く力」の大切さに注目しながら考えてみようと思います。
神職のコミュニケーション
我々のような神職、聖職者と言いますと、神社の中でひたすらお祈りをしている人という印象もございますが、実際はそうではありません。
神職は沢山の人と関わります。何気なく神社にご参拝くださる方々、日頃からご崇敬を賜っている方々、地域の氏子総代の皆様、同じ神職の皆様。神社はたくさんの人とのありがたい繋がりによって成り立っているからです。
神職の仕事とは、人と関わること、コミュニケーションであるといっても過言ではないでしょう。
しかし、そもそも神職には第一にコミュニケーションをとるべきお相手が存在します。
神様です。
神社に参拝しますと、頭を下げて、手を打ってお願い事をいたしますね。心の中であっても、声に出す祝詞であっても、お願い事を神様に申し上げる、いわば神様とのコミュニケーションであることには変わりません。
しかし、人と人とのコミュニケーションと、神と人とのそれでは、決定的に違うところがひとつございます。それは、神様がお返事を下さることは基本的にないという点です。
所謂御利益のような形で神様が答えてくださることは多くございますが、それでも人と同じようにはいきません。
神様は聞き上手
これは何も今に始まったことではありません。平安の初期から中期にかけて編まれた詳細な古代の法典に「延喜式(えんぎしき)」がございますが、ここには当時の朝廷で使用されていた祝詞が収録されており、現存する祝詞の中では最古のものの一つです。その延喜式祝詞には「聞食せ(きこしめせ)」という言葉が何度も使われています。
意味は「お聞きくださいますように」と、神様や天皇陛下など目上の方に、こちらの申し上げたことを聞いてくださるようお願いするものです。「聞食す」は現代の祝詞でも使われますが、今では「聞し召せ」と書いたほうがわかりやすいかもしれません。
今よりも神様の時代に近かった平安時代なら、昔話のように神様が直接人にお告げを下さることも多かったかもしれません。しかしそんな古い時代の祝詞でも、目に見えない神様が聞いてくださることをひたすらに願うものだったのです。つまり、聞き終わったら話すこともある人間と違って、神様は今も昔もずっと聞き手側なのです。
コミュニケーションとは「聞く」こと
コミュニケーションの取り方を考えますと、基本的には「どのような話し方で、どのような話題を選べばよいのか」といった「伝える力」を気にしがちですが、神様のようにただひたすら聞くという事も大切ではないでしょうか。
『聞く技術』(太洋社、平成 12 年)という大変素晴らしい本があります。著者の東山鉱久さんはカウンセラーで、本書には聞き手のための貴重な技術が多く載っておりますが、その冒頭の「序」にはこうあります。
仏像を見ると、耳が大きく口の小さい像が、圧倒的に多いのがわかります。つまり、神仏はわれわれの願いを聞いてくれる存在なのです。同じように多弁な聖者はあまりいません。聖者は、己を人にわからせる必要がないからです。カリスマ性はあるかもしれませんが、少なくとも私には、多弁な聖者は信じられません。
東山先生によれば、神様は聞き上手ですが、仏様も聖者様も聞き上手です。「沈黙は金なり、雄弁は銀なり」という言葉もございますが、どうやら「聞く力」は我々が思っている以上に必要なもののようです。
なぜでしょうか。
我々は言葉を使って話をします。英語や中国語は習わないとわかりませんが、日本語は勉強しなくても話すことができます。なぜならば、生まれた時から言葉をしゃべれるように大きくなるまでの間、親御さんや先生が話しかけてくれたり、大人が会話しているのを聞いたりしながら、段々と覚えていくからです。
また、大人になっても、全く知らない人の話や、全く知らない分野の話をいきなりすることはできませんね。本やインターネットで知るのも良いですが、大抵は知っている人から詳しいことをよく聞いて、はじめて共感しながら話をすることができるようになります。
当たり前のようなことを申し上げるようですが、ここが大切なのです。コミュニケーションの出発点は、「話すこと」ではなく「聞くこと」なのです。
考えてみれば、コミュニケーションを取りたくなるような話しやすい人というのは、会話が途切れた時に「今日はどう?」と自分の話よりもこちらの話題を引き出してくれる人や、話している最中に身を乗り出して相槌を打ってくれる人、愚痴や弱音であっても最後まで真面目に聞いてくれる人など、聞き手に徹するのが上手な人が多いのではないでしょうか。
『聞く技術』でも度々触れられていることですが、上に書いた「沈黙は金なり、雄弁は銀なり」の言葉のように、昔から話すことよりも聞くことを大事にしようと言う人は沢山おられました。それでも殆どの人は他人の話を聞くよりも自分の話を話すことの方が好きです。「聞く技術」よりも「伝える技術」の方が人気なことも、それを物語っています。
しかし、人は話すのが好きだからこそ、自分の話をただ聞いてもらえることそのものに喜びを感じます。聞き手が自分を理解してくれる、自分に共感してくれるということ、それ自体が喜びなのです。
聞き手からしてみれば、積極的に聞き手になって「人の話をよく聞く」というだけで円滑なコミュニケーションをとることができ、しかも相手を満足させることができるのです。
人と人とのコミュニケーションは、話すことではなく聞くことから始まります。そして、聞き手に徹することによって相手を知り、また相手に満足してもらうことで、より円満なコミュニケーションに繋げていくことができるのです。
そして、相手にもっとこの人と話していたいという気持ちになってもらう…その為に必要なのが聞く力です。
神様を見習って、聞く力を鍛えること。これこそが、よりよいコミュニケーションを取る上での、まさしく第一歩なのです。