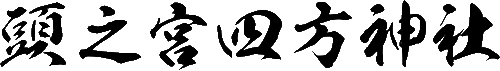神社ではたくさんのお祭りが行われています。
お正月、春祭り、秋祭り…。それらは、日本人の古来の生活様式に合うような形で、基本的には一年に一度の周期で斎行されます。 その一方で、毎月行われるお祭りも存在します。「月次祭」(つきなみさい)ともいわれるこのお祭りについて、今回は見ていこうと思います。
すぐにわかる「月次祭」のこと
月次祭とは、月ごとの決まった日に行われるお祭りで、皇室のご安泰と国の隆昌、地域と氏子崇敬者の皆様の安寧を祈り、ひいては日々の神恩に感謝を申し上げるお祭りになります。
神社で一年間行われる恒例のお祭りは、大祭、中祭、小祭に分類され、それぞれお祭りの規模や神職が著ける装束などが違います。 このうち、月次祭は小祭にあたります。屋台が出て境内が賑わう大きなお祭りよりも、厳粛な神事のみを執り行う、比較的規模の小さなお祭りといえるでしょう。
| 神社祭祀の分類 | ||
| 分類 | お祭りの例 | 装束 |
| 大祭 | 例祭など | 正装(衣冠単など) |
| 中祭 | 歳旦祭(お正月) 天長祭(天皇誕生日)など | 礼装(斎服など) |
| 小祭 | 月次祭など | 常装(狩衣や浄衣など) |
また「月ごとの決まった日」は、それぞれの神社によってさまざまに定められていますが、多くは毎月の1日、または毎月の15日などに行います。月に複数回行っている神社もあります。
それに対して、当社では、月次祭を毎月の16日に斎行しております。 毎年11月16日は、当社の例祭当日祭であり、御祭神の縁故日のなかでも最も重要な日にあたります。その故あって、11月以外の月の16日にも特別にお祭りを執り行い、神さまへお祈りと感謝を申し上げるのです。
以上をまとめますと、月次祭とは、毎月行われる比較的規模の小さなお祭りであり、皇室のご安泰と皆様の安寧を祈り、ひいては日々の神恩に感謝を申し上げるお祭りです。神社では毎月1日に行われることが多いですが、当社では例祭に準じて毎月16日に執り行われております。
古代の月次祭について
ここからは少し詳しいお話に移っていきます。
神道に関係する書籍には、「月次祭」を「つきなみのまつり」と称し、上記の事とは少し違ったことを解説しております。 こちらの月次祭とは、かつて国家及び伊勢の神宮で行われていたお祭りで、その歴史は律令制を導入した奈良時代にまで遡ります。専門的な研究は色々とありますが、その特徴は大きく分けて3つあります。
- 一つは、6月と12月の年2回行われるお祭りであるという点。当時の国家のお祭りは、5月と11月、4月と8月といったふうに、同じお祭りを年2回行うものが多くありました。今でも上半期と下半期と言ったりしますが、昔の日本人は、1年を半分に分けていたようです。
- もう一つは、月次祭を行った夜に、神今食(かむいまけ)というお祭りが行われる点です。こちらは宮中で秋に行われる新嘗祭と殆ど同じもので、天皇陛下が神さまへお供え物を上げ奉り、陛下御親らも召し上がる「神人供食」のお祭りです。
- 最後は、庶民の家の宅神祭と似ているとされている点です。月次祭を行うことが規定されている『神祇令』という古代の法典には、『令義解』という国家公式の注釈書が存在しており、そこでは「即ち庶人の宅神祭の如し」と解説されています。宅神祭については諸説ありますが、今でいう神棚で行う各家庭のお祭りと理解すればわかりやすいでしょう。
少し難しいお話ですが、要しまするに、いま神社で行われている「月次祭」とは別物であることがわかります。現在の神社の月次祭は月に一度の小さなお祭りですが、この月次祭は年に2度の大きなお祭りなのです。 なお、宮中の月次祭は応仁の乱で京都が焼け野原になった際に他のお祭りとともに中絶してしまいましたが、伊勢の神宮では今も行われております。

月次祭はいつからあるのか-毎月1日のお祭りについて
それでは、現在全国の神社で行われている月次祭はいつからあるのでしょうか。
上記の通り、現在の月次祭は、多くの神社では1日に行われております。
そもそも毎月1日にお祭りや神事を行うことは、古くからなされていることであり、宮中では「内侍所御供」として、寛平年間(平安時代)から行われていたことが『公事根源』(室町時代成立)という著名な文献に記されています。このお祭りは「旬」「旬日」などとも称し、今も旬祭という名で、宮中にて毎月1日、11日、21日に行われています。
毎月1日、11日、21日の神事は、奈良時代から幕末まで国家の神社行政を執り仕切っていた神祇官という役所でも「旬日」という名で、宮中のそれと同時期頃から行われていたようで、『神祇官年中行事』(鎌倉時代成立)によると、その内容の一部は正月の行事に準じたものであったようです。
このように、毎月1日もしくは1のつく日に神事が執り行われたのは、正月に準じるめでたい日として吉日とみなされた為でしょう。後世のものながら、室町時代の『康冨記』には、嘉吉2年7月1日に貴人の邸宅に訪問したことを「朔日(ついたち)の礼」と称していますが、このように毎月1日を他の日とは違う吉日とみなす風習は多く見られます。
奈良の春日大社でも、平安末期ごろから宮中に倣う形で旬祭が行われていたことが『春日社年中行事』などの文献からわかりますが、このような例から、月ごとのお祭りとそれを1日に行う例は多く存在し、少なくない神社もそれに準じていただろうことが拝せられます。 また、それとは別に、願い事を叶えるために月に一度必ず神社に参拝する「月参」という習俗も、平安頃からあったようです。そして、伊勢では毎月1日に伊勢の神宮へ参拝する「朔日参り」もいつの頃からか行われておりました。
「月次」は「月毎」の意味?
このように、「毎月行うお祭り」が平安時代頃から既に存在し、またそれが「1日」を吉日とみなす考え方とも結びついていたことがわかります。当社の「吉日」は16日である訳ですが、毎月1日はいわば日本人の吉日であり、宮中や特別な吉日や縁日を定めていない神社でも、お祭りをしたり参拝に伺うにはうってつけの日であったというわけです。
それでは、この神社で毎月行っているお祭りが、なぜ「月次祭」と名付けられたのでしょうか?
これまで平安時代や室町時代のお話をしていましたが、時は下って江戸時代になると、古典研究を背景に日本人本来の精神を発見しようとする「国学」という学問が興ります。その大成者と呼ばれている大学者本居宣長は、古典を通じた神道の研究でも多くの成果を遺しております、彼の随筆集に『玉勝間』があります。 研究の分野だけでなく、読み物として高い評価を得ているこの『玉勝間』ですが、この中には上記の朝廷における「神今食」と「月次祭」を考証した段があります。そこには
(前略)まずその月次祭は、三百四座の神たちに、幣帛を奉り給う祭りである。それを月次祭と名付ける理由は、月毎に奉り給うべきものを、合わせて二度に奉り給うにて、六月には、その年の七月より十二月までの(新しく作ったお供え)を奉り、十二月には、来年の正月より六月までのを奉り給うのである。(カッコ内及び現代語訳筆者)
とあります。朝廷の行っていた6月と12月の月次祭は、本来は毎月行っていたお祭りであったと解釈しているのです。
現代の『国史大辞典』では、この説について「名称からの推定で、実証的な根拠はない」とされていますが、少なくともこの説が登場した事は、現在の「月次祭」に大きな影響を与えていると考えられます。
毎月1日(朔日)を特別な日、めでたい日とし、毎月1日に神社でお祭りや参拝を行っていたことが、江戸時代頃になって前記の『玉勝間』などから「月次祭」という名称及び「月次=月毎」の解釈が全国的に知られるようになっていき、やがては各神社で、毎月行うお祭りを「月次祭」と名付けるようになっていったのではないでしょうか。
つまり、元々は別のものであった月次祭という「名前」と、1日など毎月決まった日にお祭りを行っていたという「中身」が、江戸時代頃から現代にかけて「合流」したことによって、現代の「月次祭」という名称の祭典が生まれたと結論付けることができます。
古代朝廷の月次祭と現代の月次祭は全くの別物であるといえますが、但し、「皇室の安泰と、それによってもたらされる国中の平和」を祈るという点では、古代の月次祭の祝詞と、それを踏まえた現代の神社の月次祭の祝詞は共通しています。 例えば昭和12年の『神道大辞典』では、朝廷と伊勢の神宮の月次祭を解説した後、そのまま同じ項目内で神社の月次祭の例を記しています。形は違っても、精神的な面では両者は変わらないということでしょう。
月次祭を行えること
当社では、16日の前後にInstagramなど各種SNSを通して、今月の月次祭を執り行った旨を皆様へお伝えしております。
全国では過疎化や少子化が深刻であり、氏子崇敬者さんたちを集めて月次祭を行いたくても難しいお社が増えております。そんな中で、毎月の月次祭を執り行い、皆様、ひいては日本国とその他世界中の人々の安寧を祈ることができるのは、偏に氏子崇敬者の皆様のご奉賛のお陰であります。 ご神恩への感謝は勿論ですが、毎月の月次祭を無事執り行うことができたと、SNSを通してでも皆様へとお伝えできること。それ自体が、神職にとっては大きな喜びなのです。